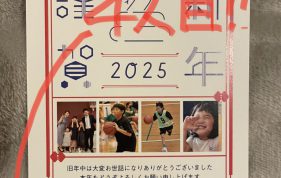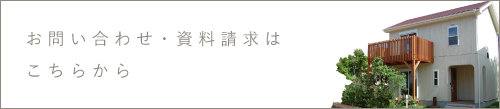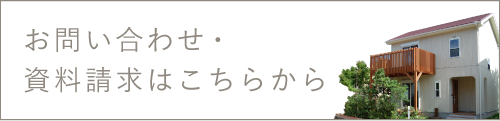教育はサービス業ではない
公立学校でも「選択」される時代に突入すると、公私を問わず「差別化」ばかりを意識しすぎて、「本来のあるべき姿」がないがしろにされつつある学校も多いようです。
ある学校では
「躾はすべて学校にお任せください」
が生徒募集の「売り」だとか。
教育改革の論点と言えばすぐに、「時代(というよりも保護者)のニーズ」や「国際化社会」に対応するというキーワードが出てきます。
お産が今も昔もこれからも同じであるように、教育の基本というか、基礎というのも今も昔もこれからも、そして万国共通的な要素というのがあるのではないでしょうか。
例えば、世界で活躍するプロアスリートが象徴するように、幼少期の教育という点では「基礎をしっかり学ぶ・叩き込む」を徹していて、それを継続・応用し続けた結果、一流の選手になっていると思います。
「ニーズに対応する」というのは一見万能のようですが、その中身を吟味すると実際には「目先の利益」に過ぎないものや対応すべきではないものも含まれます。
世の中は刻々と変化しているわけですが、だからといって目先の変化に目先だけ対応するような行為というのは「教育」とは言えません。国家そのものが目先をしのぐことだけを最優先する社会となっているからこそ、「教育」に託された意味は大きいように思います。
誰かが言いました
「教育はサービス業」だと
サービス業という言葉が、「ニーズに対応する」という意味で使われているのだとすると、それは違うと思う。敢えて言うなら「教育は、教育である」ではないか。
情報が氾濫し、無限の選択肢が存在している社会だからこそ、基礎をしっかり見極め、教えることこそが「真のニーズに対応すること」だと思います。基本問題が解けずに、応用問題が解けるわけはありませんから。